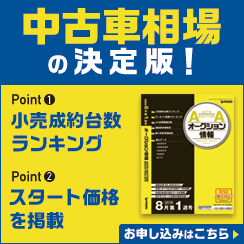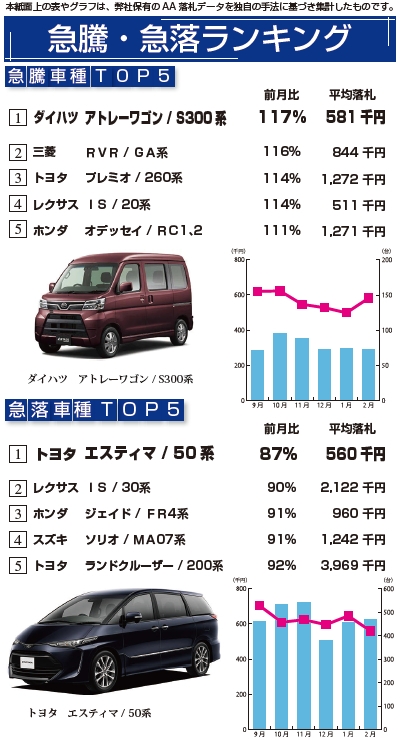-
【この道のプロ】Vol.005 cantera(東大阪市)
 2025年06月30日
cantera
2025年06月30日
cantera
-
【JU特集】塚田新会長・理事長体制がスタート
 2025年06月25日
JU中販連・JU中商連
2025年06月25日
JU中販連・JU中商連
-
【特集】急拡大するレンタカー市場にビジネスチャンス
 2025年05月29日
2025年05月29日
-
山川博功コラム VOL.006(最終回)
 2025年05月27日
ビィ・フォアード
2025年05月27日
ビィ・フォアード
-
【特集】2024年度の自動車業界を振り返る
 2025年04月23日
2025年04月23日
 西暦元号早見表
西暦元号早見表