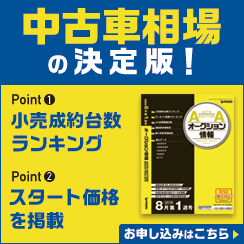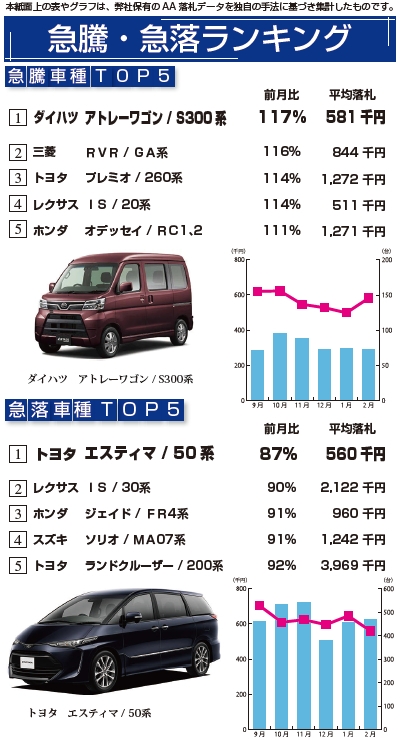-
【バディカ連載 Ver.2.0】Vol.011 欲望の壁を破壊せよ
 2024年04月23日
BUDDICA
2024年04月23日
BUDDICA
-
【特集】2023年度を振り返る
 2024年04月23日
2024年04月23日
-
【特集】サブスク人気などを背景に拡大する「オートリース市場」
 2024年03月28日
2024年03月28日
-
【バディカ連載 Ver.2.0】010 競合の壁を破壊せよ
 2024年03月28日
BUDDICA
2024年03月28日
BUDDICA
-
Web限定【自動車業界特化型税理士新連載企画】「個人事業」で車屋を…
 2024年03月26日
自動車業界特化型税理士 酒井将人
2024年03月26日
自動車業界特化型税理士 酒井将人
 西暦元号早見表
西暦元号早見表